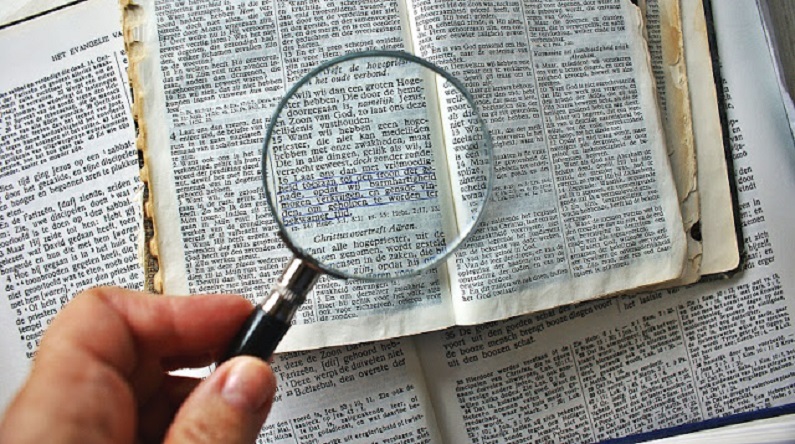副業のひとつとして、よく耳にする「WEBライター」という職業ですが、みなさんはどんな仕事か想像ができますか?
WEBライターとは簡単に解説すると、WEB上に載せるための記事や文章を作る職業です。
WEBライター未経験の方にとっては「何から始めればよいか?」など迷う部分もたくさんあるかと思います。
そこで今回は『WEBライターとは一体どんな仕事?必要なスキルや仕事例を紹介』と題し、WEBライターの仕事内容や最低限必要なスキルなどについて解説します。
WEBライターとはどんな仕事なのか?仕事例を紹介!

WEBライターとはどんな仕事かわかりやすく説明すると、WEB上に載せるための記事(文章)を作る職業です。
主にWEBライティングとして有名な仕事としては
〇自社のオウンドメディアやブログに掲載するSEO記事
〇商品・サービスの魅力を伝えるための記事
〇商品・サービスに関連したコラム記事
〇ニュースサイトに掲載する記事
など、さまざまなジャンルが存在します。
紙媒体への掲載ではなく、WEB上が掲載メインとなるのが、WEBライターという職業となります。
WEBライティングとは?どんな種類があるのか

上記『WEBライターとはどんな仕事なのか?仕事例を紹介!』にも簡単に仕事内容を紹介しましたが、この段落ではより詳しく解説します。
SEOライティングとは検索エンジンにヒットさせるもの
SEOライティングとは、検索エンジン(GoogleやYahoo!など)に検索されやすくし、流入や最終的なコンバージョン(商品やサービスへの問い合わせ、購入など)数を狙って書く文章を意味します。
主にユーザーが検索してくれそうなキーワードを盛り込み、執筆していく流れとなっています。
ほかにも、例えばGoogleの上位ランクに掲載されるための対策も考えつつ、書いていかなければいけません。
セールスライティングとは購買意欲を向上させるもの
セールスライティングとは、商品・サービスを販売するために、ユーザーの購買意欲が高まるような、文章を書くものです。
主にメールマガジン(メルマガ)やLP(ランディングページ)といった部分で、活用されます。
コラムライティングとは経験・意見を織り交ぜて書くもの
コラムライティングとは、あるお題に沿って自身の意見や経験を織り交ぜつつ書くものです。
例として、商品やサービスを利用した経験があれば利用者目線で書く、といった感じです。
取材ライティングとは人物や店舗などに直接話を聞く
取材ライティングとは、人物やお店などに直接話を聞いて記事にするものです。
最低限の質問内容をベースに、話す内容によってはアドリブで質問を考えて聞く必要があるため、コミュニケーション能力をある程度養っておかなければいけません。
コピーライティングとはキャッチコピーと広告文を作る
コピーライティングとは、企業、商品やサービスのキャッチコピーと広告文を作成するものです。
広告やポスターなどに使われるもので、キャッチコピーで目を引かせたり、購買意欲をかき立たせたりし、広告文で商品やサービスを想像させる内容を書きます。
PRライティングとは企業の広報活動を支援するもの
PRライティングとは、企業の広報活動やPRをサポートするものです。
企業が保有するメディア(ブログやSNSなど)を活用してPR活動を行い、ユーザーに直接、商品やサービスなどの魅力を伝えます。
シナリオライティングとはストーリーなどを書くもの
シナリオライティングとは、ストリーリーやセリフの流れを作成するものです。
最近では、動画投稿サイト(YouTubeなど)に投稿する動画用のシナリオライティングの需要がああります。
WEBライターになる方法としておさえておきたいこと

WEBライターと一言でいっても、さまざまなジャンルのライティング作業があることがわかります。
では、次にWEBライターになるためにはどうすればよいか?について解説します。
※筆者の体験談、経験してきたことを織り交ぜて解説しておりますので、参考程度にご覧ください。
自身がWEBライターに向いている人かどうか
はじめに、自身がWEBライターに向いている人かどうかの、適正を考えなければいけません。
よく「国語力、語彙力がないとだめ」と言われますが、必ずしもそうとは言い切れません。
分からない言葉や表現方法に関しては、執筆していくうちに「どんな言葉があるか」「どんな表現方法があるか」と自ら調べ学習していくので、言葉を知らないのは特段問題ではありません。
批判的、誤認されるような表現方法さえ避けてしまえば、文章はそれとなく書けます。
言葉は自然と覚えていくので、まずは「コミュニケーション能力」「リサーチ力」を養うことができるかに焦点を当てて、自身がこの2つのスキルを磨けるかどうかで、適正かどうかを考えた方が良いかもしれません。
WEBライターとスタートするには就職かブログを運用
WEBライターだけでなく、ライター職全般に言えることですが各ジャンルには「文章の書き方」というものがあります。
いきなりWEBライターと名乗ってはじめても、書き方を知らないと案件はもらえない可能性が高いです。
また、仮に仕事を手に入れても書き方がわからないと筆が進まず納品できません。
一番の近道は未経験OKのライター求人の企業に就職
まず、学ぶ方法として一番簡単なのは、ライティングの基礎となる新聞社、出版社、自社メディアを展開している企業に就職し、そこで学習していくことが最大の近道です。
新聞社独自の記事の書き方、出版社独自の執筆方法、自社メディアであれば広報誌やWEBメディアへの書き方、といったさまざまな手法があり、仕事をしながら各方法を学ぶことができます。
書き方の基礎ができあがれば、それをベースにあらゆるライティングに挑戦しやすくなります。
就職が難しい場合は自らブログ運用をする
ただ、「未経験WEBライター募集」「未経験新聞記者募集」という求人を探し出すのも、少々ハードルが高いです。
この場合は、自らブログを立ち上げて独学でライティングを学ぶ方法があります。
ブログを立ち上げて、最初はさまざまな優秀なブログなどを参考に執筆方法を学び、ある程度書き方を覚えたら実際に店舗や人物への取材を試みるとよいです。
この2つを行うことで「リサーチ力」と「コミュニケーション能力」を養うことができます。
ブログのプラットフォーム内には、閲覧数などの効果測定が搭載されているので、どんな記事がよく読まれたかをチェックできます。
こうした効果測定を必ず見ることで、将来的な記事の傾向と対策が立てられ、スキルアップにつながります。
また、SEOライティングや取材ライティングの記事がある程度、ブログ内に掲載されたら、ポートフォリオ(参考資料)として提出できるので、案件を取る際に活用することができます。
取材ライティングからSEOライティングがおすすめ

経験談と独自解釈とはなってしまいますが、WEBライターを目指すなら、取材ライティングからはじめ基礎を学んだら、SEOライティングへと移行するとWEBライターになりやすいです。
筆者の場合、新聞記者からスタートし、現在はIT企業の自社ブログでSEOライティングを仕事としています。
取材ライティングから開始してSEOライティングに移る方が、なぜWEBライターになりやすいか?について解説します。
取材ライティングは記事の基礎や対話が学べる
取材ライティングは主に本文を要約した前文、本文で構成されており、読む側がスムーズに情報が入ってくるような構成となっています。
こうした構成を学ぶことができます。
また、取材ライティングのいいところは、実際に人や店舗へ直接取材をするという点です。
インタビュー対象への質問をしたり、Q&Aのやり取りだけでなく合間の会話をつなぐためのアドリブも養われます。
そのため、執筆活動以外でのコミュニケーションにも役立つスキルが身に付きます。
そのほかでは、インタビュー対象の情報が薄い場合インターネットで対象を調べて、補足情報を追加したり、あいまいな情報に関しては事実誤認が無いかを調査するといった、リサーチ力も育むことができます。
この3つのスキルを学ぶには、取材ライティングが一番覚えやすいです。
基礎を学んだらSEOライティングに挑戦
取材ライティングで、文章校正、コミュニケーション能力、リサーチ力を学んだら、SEOライティングへと移行します。
SEOライティングは主に、インターネットを介してのリサーチ、クライアントに話を聞くなど、オフィス(または在宅ワーク)内で完結することがほとんどです。
取材ライティングで得たスキルは以下の要素で活躍します。
・文章構成=記事執筆時に役立つ
・コミュニケーション能力=クライアントとのやり取り
・リサーチ力=クライアントが求める記事内容の調査、SEOキーワードの抽出
特にSEOライティングでは、リサーチ力が必要となります。
トレンドをおさえつつ、クライアントが求める記事の内容、競合他社がどんな切り口で記事を掲載しているか、検索エンジンにヒットしやすいSEOキーワードの抽出と、リサーチ力がないとSEO対策用の記事は完成しません。
ただ、他のライティングと比べて、SEOライティングはGoogle Analytics 4を活用した効果測定で、実際に掲載した記事が効果を発揮しかを確認しやすいため、仮に効果がなくてもリライトして再掲載し、改めて効果測定を行うといったPDCAサイクルが回しやすいので、失敗と成功を繰り返すことのできる分野なのでライティング初心者にはおすすめです。
理由としては、PDCAサイクルを回すことで、よりライティングスキルがアップするので、WEBライターとして成長しやすい環境だかれです。
まとめ
本記事はいかがでしたか?
「副業としてWEBライターがおすすめ」とよく聞きますが、どんな仕事でも簡単にできるほど甘くないのが現実です。
しかし、一歩ずつWEBライティングに必要なスキルを学べば、今回紹介した仕事例のような世界でライターとして活躍することができます。
筆者の場合、新聞記者として文章構成、コミュニケーション能力、リサーチ力を学び、独学でSEOライティングに挑戦し、現在は新聞記者兼WEBライターとして生計を立てています。
自社ブログを運用しているのにも理由があり、取材や記事内容を1つのジャンルにとらわれず、いろんなジャンルに挑戦することで、日々スキルを磨いています。
「副業でちょっとした小遣い稼ぎ」という考えではなく、まずは「自身がWEBライターに向いている人か」「小遣い稼ぎではなく、まずは仕事のおもしろさを知る」というところからはじめてみてはどうでしょうか?
以上、『WEBライターとは一体どんな仕事?必要なスキルや仕事例を紹介』でした。